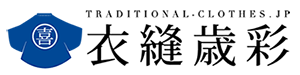-歳時記-
種子島鉄砲祭り

日本の歴史に影響を与えた「火縄銃」と保存会の活動
日本全国で火縄銃の保存会は50以上あり、その中の一つである種子島火縄銃保存会の様子をご紹介します。
「火縄銃」は、1543年(天文12年)種子島(現在の鹿児島県種子島)に漂着した3名のポルトガル人によって伝えられました。
いち早く火縄銃を取り入れた、種子島時尭
ポルトガル人から銃を披露された種子島氏14代当主「種子島時尭」(たねがしまときたか)は、その威力に感じ入り、金2,000両で2挺の銃を購入した。種子島時尭は家臣らに、ポルトガル人から火薬の調合を学ぶように言いつけ、自身は射撃について学んだとあります。
また、銃1挺を鍛冶職人の「八板金兵衛」(やいたきんべえ)に調べさせ、生産に成功した。
和泉堺(現在の大阪府堺市)の商人「橘屋又三郎」(たちばなやまたさぶろう)と、紀州(現在の和歌山県)の僧侶「津田監物」(つだけんもつ)が、種子島で火縄銃の製造技術を学び、故郷へ持ち帰ったことで堺と紀州は火縄銃の一大生産地となりました。
伝来した火縄銃は、藩主「島津義久」(しまづよしひさ)へと献上されました。また同時に火縄銃の火薬の調合法を伝えており、国産化された火縄銃を島津氏はいち早く戦場に投入します。
火縄銃を使った戦で最も有名なのが織田信長
あの有名な「3段撃ち」の戦法を編み出しました。
「3段撃ち」とは、鉄砲隊を3段に分け、最前列が射撃している間に次列が点火、最後列が弾を込めるという戦法です。
当時武田軍は、最強と名高い騎馬隊を有していたため、織田信長はその対策として連子川に沿って馬防柵(ばぼうさく)を設け、
その内側に3,500名の鉄砲隊を配したのです。
この戦いで武田軍は10,000人以上の死傷者を出したと言われています。
銃火器を主とする歩兵戦術が騎馬に代わる新しい時代の戦い方の主流にとって代わることを示していました。
火縄銃は、瞬く間に全国の武将達に伝播し実戦に投入されるようになっていきました。
また、島津家も鉄砲戦術に優れており、九州を平定できたのはこの火縄銃の存在が大きかったと言われています。
今年で種子島に鉄砲が伝えられてから480年になります。
コロナで中止されていましたが、
鉄砲伝来の記念式典が4年ぶりに開催されました。
鉄砲伝来を種子島火縄保存会のメンバーが火縄銃の空砲の試射を披露しました。
市街地を行進しながら試射するのは種子島と堺だけだそうです。
火縄銃でも本物とレプリカがあり、種子島鉄砲隊が持っているのは、本物の火縄銃です。空包といえど、その轟音は迫力があり、「放て」の姿は勇壮で見応えがあります。

- また、種子島開発総合センター「鉄砲館」では、ポルトガル初伝銃や伝国産第1号銃をはじめ、国内外の古式銃約100点を展示しています。
種子島鉄砲隊の衣装を担当したのは、美夜古企画です。
ご相談、ご依頼は、美夜古企画までお待ちしております。