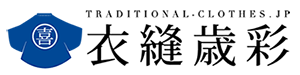-歳時記-
流鏑馬のお祭り

流鏑馬は、日本の古式弓馬術です。武家社会で行われた騎射の一種で、馬術と弓術を組み合わせたもので、 疾走する馬に乗りながら鏑矢で的を射るという技術であり儀式です。競技としてもあります。
流鏑馬の起源は、6世紀、欽明天皇が世が乱れたのを憂い、宇佐の地(現在の大分県)において「天下泰平、五穀豊穣」を祈願して、三つの的を馬上から射させられたことが始まりとされています。
宇佐神宮では、令和元年に天皇陛下御即位の慶事を寿ぎ、以後毎年恒例になった神事です。
流鏑馬で使用する衣装についてご紹介します。
武士が山野に狩する時や流鏑馬(武士の競技の一種)の時の着用する衣装が狩装束です。萎烏帽子なええぼしをかぶり、その上より藺草で編んだ綾藺笠あやいがさ をかぶる。中央は巾子(こじ)といい、髻(もとどり)をいれる為に高くなっています。下には水干(あるいは直垂)を着、射籠手(いごて) または、弓籠手を左腕につけ、手には鞢(ゆがけ)(革手袋のこと、流鏑馬では手袋という)をはめ、腰に行縢 (むかばき)という鹿の夏毛革の覆いをつける。足にはくのは物射沓(ものいぐつ)という。腰に太刀、腰刀を佩び、空穂(うつぼ)(矢を入れるもの)(流鏑馬の時は箙(えびら))を吊して弓を持ちます。
quote:日本服飾史
イラストでの解説
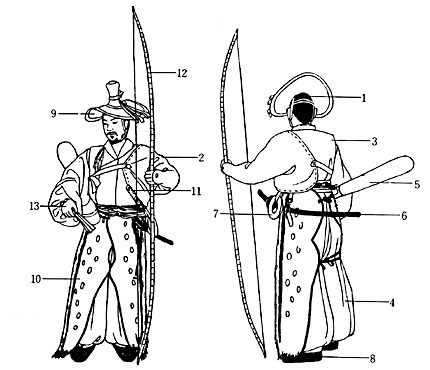
- 1.萎烏帽子-enaboushi
- 2.射籠手-igote
- 3.水干-suikan-
- 4.水干の下しも-shitashimo of suikan-
- 5.空穂-utubo-
- 6.革包太刀-kawatuduminotachi-
- 7.弦巻-turumaki-
- 8.物射沓-monoigutsu-
- 9.綾藺笠-ayaigasa-
- 10.行縢-mukabaki-
- 11.腰刀-koshikatane-
- 12.弓-yumi-
- 13.鞢-yugake-

「あれが日本の侍か!」と日本文化への感心の高まり
今では、日本だけでなく、海外でも人気の流鏑馬です。 ぜひ、流鏑馬をご観覧いただきたいものです。
九州で有名な流鏑馬お祭りをご紹介します。鹿児島の住吉神社の流鏑馬をご紹介します。
住吉神社の流鏑馬は、県下三ヶ所(他に肝付町高山の四十九所神社,日置市吹上町の大汝牟遅神社)で行われる流鏑馬の一つです。
国家安泰・五穀豊穣のほかに年占いの性格も持ち、農民が参加する収穫感謝の色彩が強いです。流鏑馬に先立ち神前では奉幣の儀が行われ、次いで馬場入りとなります。
現在は中・高生がこの大役を果たします。参道を鳥居から神社へ向かって約300メートル馬を馳せ、勢いよく走る馬上から途中3か所の的を射る。これを3回繰り返します。当たり的を持ち帰って家を葺けば栄えると言われ、また矢が的に当たるほど翌年は豊年と言われているています。昭和56年に県指定無形民俗文化財となっています。
美夜古企画では、流鏑馬の衣装を提供しております。美夜古企画では、弓籠手、水汗、直垂、狩装束、巻狩などの衣装を制作しています。
ご相談、ご依頼は、美夜古企画までお待ちしております。